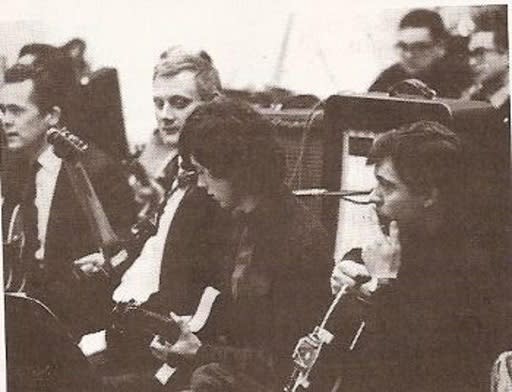ダンエレクトロの日本代理店である
キクタニミュージック株式会社によれば、ダンエレクトロのエレクトリック・シタール、通称「ベイビー・シタール」と呼ばれるモデルがリイシューされたということである。
そもそも
ベイビー・シタールとはどんなものかといえば、そのオリジナルモデルは1968年から1969年までの間、つまりダンエレクトロが終焉を迎える末期に生産されたもので、60年代後半に一世を風靡したエレクトリック・シタールの第2弾であり、本物のシタールの共鳴胴に似せた丸っこいボディシェイプが特徴のもの。
私の記憶が確かであれば、前回ダンエレクトロからコーラルのエレクトリック・シタールがリイシューされたのは2012年の10月のことであった。これは全くといって突然のことであり衝撃的な事件であったが、今回の「ベイビー・シタール」のリイシューもそれに劣らず衝撃的であるといえるだろう。いずれにせよ、今回もまたごく少数の入荷ということなので、市場に現れた途端に一瞬で完売し、あとかたもなく消えてしまう「幻のリイシュー」となりそう。
今回のベイビー・シタールのリイシューは本家ダンエレクトロのあずかり知らぬところで動いていると推測される。ギターのリイシューに関してコンサルタント的な役割を担ったスティーヴ・ソーストは以前あるインタビューで、エレクトリック・シタールをリイシューするかと尋ねられたとき、コスト的な問題からそれはないだろうと答え、エレクトリック・シタールの音が欲しければダンエレクトロのギターのブリッジをゴトー製のシタール用ブリッジにリプレイスすればいいだけのことと言っていたのである。
思い出してみれば、昔からダンエレクトロには本家と関係なく勝手に製品が出回るところがあって、本家のカタログにはない仕様やモデルが存在し、謎が謎を呼んでいた。最近でもアリゲーターフィニッシュではない‘67 HEAVENが日本限定で発売されたし、ダブルネックのリイシューもあったが、これらはアメリカでは発売されなかったモデルである。直近で謎の仕様といえば、
ショートホーンの12弦モデルにfホール(ダミー)のついたものがどうやら出回っているようなのであるが、これは逆にアメリカだけで他の国で販売されてはいないようである。このギターのタバコサンバーストは今回のベイビー・シタールと風合いが似た感じになっていることから、同じ工場で生産されたものだと考えられるが、詳細は今のところ不明である。
現在ダンエレクトロのギターをつくっているのは韓国のイタリアギターズである。このブランドではビザール的なデザインのギターを様々つくりだしているが、その中にはコーラルのエレクトリック・シタールをデフォルメしたModenaというモデルもある。そういうところであれば、その気になりさえすれば余剰パーツを使い回してダンエレクトロのエレクトリック・シタールをリイシューしたり、謎仕様を気まぐれに生み出したりするのはそれほど難しい仕事ではないわけだ。
さて、今回のリイシューとオリジナルモデルを比較してみると、やはり細かい部分に違いがある。一番大きな違いといえば、座って弾くときに足に乗せる金属のレッグ・レストがリイシューにはついていないということだ。その次に目立つ違いはブリッジとピックアップの間の距離で、オリジナルはブリッジのすぐ前にピックアップがあるが、リイシューは少し離れた位置になっている。さらにオリジナルにはピックアップの周囲に金属のエスカッション的なものがあるのだが、リイシューにはない。加えてテールピースの形状とストラップピンの位置が違う。
ベイビー・シタールは何回か落札し損ねたという因縁もあって、いつかは手に入れてやろうとひそかに狙ってはいたのだったが、もともとの製造本数が少なかったせいか、ここ数年はebayでも見かけることがなくなっていた。わりとよく見かけるコーラルの方はといえば、こちらは相場が高止まりといった状況にある。こうした事情があって、私としては、エレクトリック・シタールの入手に関してオリジナルにこだわるのを諦めるほかなくなってしまったのである。そんなわけで先日ジェリー・ジョーンズのコピーモデルを手に入れたところなのであるが、このタイミングでのベイビー・シタール、それがリイシューであろうと何であろうと、ここで会ったが百年目、きっちり手に入れることにしたい。